お釈迦さまが悟りに至られた聖地インド・ブッダガヤには、「大菩提寺」という寺院が建っています。私も参詣させていただいたことがありますが、同寺は全世界の仏教徒にとって極めて大切な場所であります。その大菩提寺が今、歴史的な瞬間を迎えるかもしれないということで、当ブログでもご紹介させていただこうと思います。
そもそも「ブッダガヤ大菩提寺」とは、仏教発祥の聖地でありますので、おそらく日本の多くの方がインドの仏教徒が管理しているお寺だと認識されているかと存じます。しかし実はそうではありません。インドの複雑な歴史、混沌とした宗教文化の中で、長らくヒンドゥー教徒による管理が続いており、仏教徒にとってはとても歯がゆい状況なのです。
そんな中、岡山県出身で半世紀にわたってインド仏教再興のために尽力されている佐々井秀嶺師は、全インドの仏教徒とともにブッダガヤ大菩提寺の返還を求める活動(啓発アピールやデモ行進など)を1992年より行い、2012年からはインド最高裁へ訴えて、大菩提寺の管理権を仏教徒の手に取り戻すための裁判を開始しました。それから13年間、インド国内におけるヒンドゥーとイスラムの宗教対立や新型コロナの影響でなかなか結論が出ませんでしたが、ここへきてインド最高裁は「結審」することを明言。今月5日、ついに判決が言い渡されるというのです。
先月には、岡山市佛教会としてこの裁判に対する緊急声明を発表しました。どうか全世界の仏教徒の悲願が成就するよう至心に祈念するところでございます。
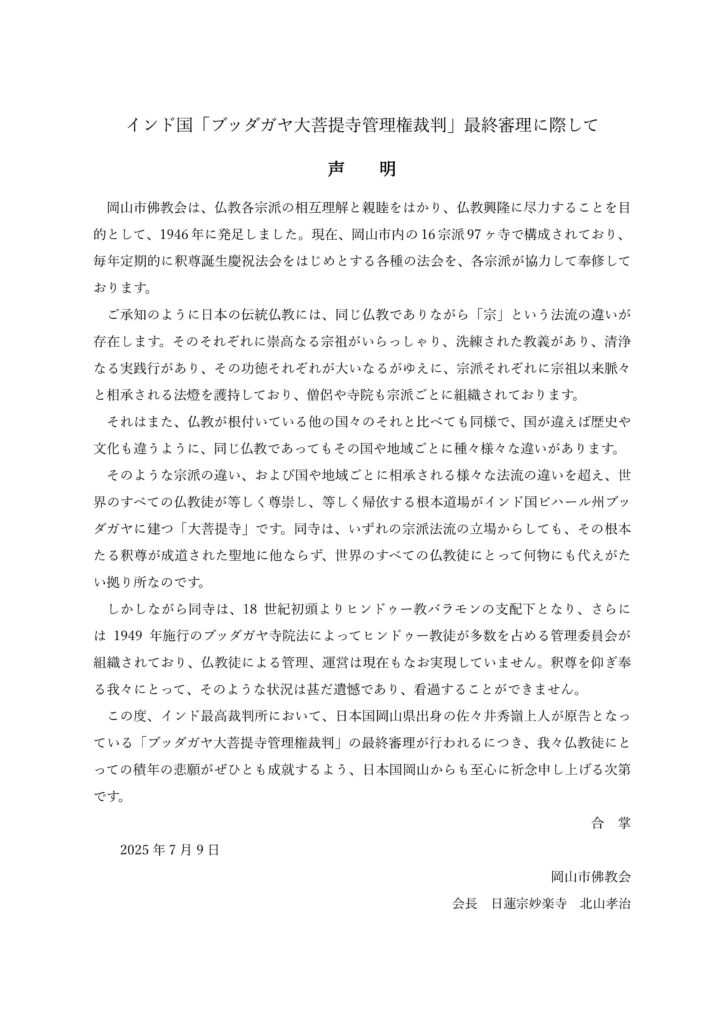
以下、佐々井秀嶺師の公認後援会「南天会」の機関紙『龍族』5号(2015.12.7)を参照させていただき、大菩提寺についての歴史的経緯を略記いたします。
お釈迦様が入滅された後、3世紀になってマウリヤ王朝アショーカ王が大菩提寺を開創しました。ところが13世紀、同寺院が位置する東インドへイスラム軍が侵攻します。同地の仏教徒は、53メートルもある大菩提寺の大塔をなんとか守ろうと、尼蓮禅河の砂を以って埋め隠したのだそうです。それから約600年後の1880年、イギリスの考古学者アレキサンダー・カニンガムは発掘調査を行い、大塔は再び姿を現しました。
しかしながら、大塔が砂に埋まっていた600年の間に、同寺院が位置する地域がヒンドゥー教徒の居住地へと変わってしまっていました。1947年、インドはイギリスから独立し、ブッダガヤ大菩提寺には管理委員会が設置されることになりました(1949年)が、そのような歴史的経緯もあって同委員会はヒンドゥー教徒が多数を占める構成(管理法によって規定)となってしまいました。以来、現在にいたるまでその状況が続いています。
佐々井秀嶺師は、同寺院の管理法がインド憲法に違反しているとして、その無効、廃止を訴えています。
より詳しく知りたいというお方は、南天会のホームページをご覧ください。
